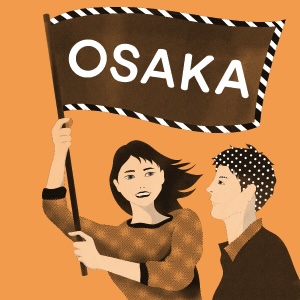1- 石切劔箭神社<東大阪>
2025.02.20
-
 ON THE TRIP旅の体験をふくらませる音声ガイドアプリON THE TRIP とは、まるで美術館の音声ガイドのように、あらゆる旅先の神社や仏閣、絶景、あらゆる観光スポットで、その場で楽しめるオーディオガイドを提供。 アプリをダウンロードすれば、あなたのスマホが自分専用のトラベルガイドに!
ON THE TRIP旅の体験をふくらませる音声ガイドアプリON THE TRIP とは、まるで美術館の音声ガイドのように、あらゆる旅先の神社や仏閣、絶景、あらゆる観光スポットで、その場で楽しめるオーディオガイドを提供。 アプリをダウンロードすれば、あなたのスマホが自分専用のトラベルガイドに!
オーディオタイムトラベルは、ガイドを聴きながら大阪の旅を楽しんでいただける記事になります。本記事では音声ガイドの一部をお楽しみいただけます。オーディオ全編はON THE TRIPアプリで体験できます。
A-1|石切劔箭神社・絵馬殿
絵馬殿(えまでん)についたら、まずは屋根を見上げてみよう。立派な剣と矢を見つけることができる。神社名の「石切劔箭(いしきりつるぎや)」は、強固な岩をも切り裂き、貫くほどに御祭神の力「御神威(ごしんい)」が偉大である様をあらわしている。
はるか昔、記紀神話(ききしんわ)時代。天照大神から「十種の神宝(とくさのかんだから)」をさずかった「饒速日尊(ニギハヤヒノミコト)」。この地に降り立ち、先住していた一族の長、長髄彦(ナガスネヒコ)の妹と結ばれ、生まれたのが「可美真手命(ウマシマデノミコト)」だ。石切神社ではこの二柱(ふたはしら)の神様を御祭神(ごさいじん)として祀っている。
実はこんな物語もある。神武天皇が世を平定するために東へと進み、この地に入ったとき、ミコトはすでにこの地を治めていた。突然現れた神武天皇(じんむてんのう)に長髄彦は激しく抵抗したが、ミコトと神武天皇が天孫(てんそん)の証である天羽々矢(あまのははや)を互いに示し合うことで、共に天照大神(アマテラスオオミカミ)の子孫であることがわかった。
そこでミコトは長髄彦に配下に入るように諭し、ここに大和国(やまとのくに)が建国したのである。その後、ミコトの一族は「物部氏(もののべし)」となり、天皇に仕えることとなった。

A-2|石切劔箭神社・穂積殿
本殿の北側にある穂積殿(ほづみでん)。「穂積(ほづみ)」とは先ほどの物語に出てきた「物部氏」の氏族(しぞく)のひとつ「穂積氏」の氏名(うじな)である。そして代々石切神社の祭祀(さいし)を継承しているのは、穂積姓から転じた木積(こづみ)氏である。
石切神社は「でんぼの神さん」として知られているが、これは「伝法(でんぽう)」が由来とされる。伝法とは、木積(こづみ)氏に古来から伝わる門外不出の秘法。また関西の言葉で「でんぼ」は「腫れ物、できもの」のこと。石切さんに参ればでんぼが治るとお参りする人が後を絶たない。
この穂積殿には通常立ち入ることはできないが、1階には宝物館があり、年に数回公開されている。石切神社所蔵の数々の御神宝(ごしんぽう)を見ることができるので、是非その時にお参りしてみてほしい。

A-3|石切劔箭神社・本殿(百度石)
境内の前に立つと2つのお百度石(ひゃくどいし)の間を 何度も行き来し、お参りしている人の姿を見かけるだろう。日本では昔から「神様に百度お参りすると願いが叶う」と言う「お百度参り(おひゃくどまいり)」が行われており、ここでもたくさんの人がお百度参りを行っている。
境内右手にある授与所、もしくは崇敬会館(すうけいかいかん)で「お百度ひも」を手に入れることができる。一周まわるたびに、お百度ひもを折って参拝すれば、「今、何回目なのか」と迷わず参拝することができるだろう。
「でんぼの神さん」として知られる石切神社だが、腫瘍を断ち切るということから「ガン封じの神さん」としても信仰されている。現在は平和な世の中になり、医療が発達し、寿命が伸びた。病気に悩みながらも、折り合いをつけて生きていかなくてはならない時代。石切さんは、そんな悩み多き人の心の拠り所となったのだ。
百度石の上部はすり減り、形を変えていっている。すり減った石は「私の、あの人の、病気が良くなりますように」と、人々が願いを込めた想いの丈を表しているのかもしれない。

EX:石切参道商店街
御本社(ごほんしゃ)と、生駒山の方角に15分ほど登ったところにある上之社(かみのしゃ)を繋ぐ参道に、石切参道商店街がある。商店街の中にはお菓子やみやげ物を扱う店もあるが、占いの店も多い。一体、なぜなのか。占いの話の前に、この参道の歴史について知る必要がある。
昔この地には、たくさんの水車小屋が建っていた。生駒山から流れてくる水で水車を回し、粉を挽いた。生駒の山は、修験者(しゅげんしゃ)が修行の場としており、山で生活をする彼らは植物や鉱物の専門家でもあった。鉱物のあるところに生える植物は薬になるため、採取したものを村の人と物々交換をして暮らしていた。村の人はその植物を粉にして、薬として売り出した。こうして江戸時代は、和漢薬のお店が参道に集まった。
参道が大きく発展をとげたのは、大正時代。鉄道が敷かれ、石切駅が開業すると近畿一帯から多くの観光客が訪れた。しかし時代が昭和になり、電力の発達とともに水車は次第に姿を消していった。上之社よりさらに奥に進んだ場所にある「辻子谷水車郷(ずしだにすいしゃごう)」では、復元した水車を見ることができる。
戦後、石切さんは次第に「ガン封じの神さん」としての信仰が厚くなっていく。病気と共に送る人生。行き場のない思いを抱える人に寄り添う人生相談所が、参道に増えていった。そしていつしか「占い」という形に変わっていったのだ。不安や悩みからは逃れられぬ。それなら少しでも心を軽くしたいと、何かに頼る。そんな気持ちは、昔も今も変わらないのかもしれない。

※このガイドは、取材や資料に基づいて作っていますが、ぼくたち ON THE TRIP の解釈も含まれています。専門家により諸説が異なる場合がありますが、真実は自らの旅で発見してください。
※掲載情報は2025年2月時点のものです。掲載店舗・施設に関する最新の営業時間は各店舗・施設のHPなどでご確認ください。