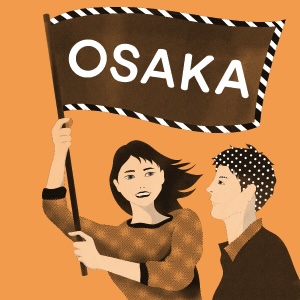2- 枚岡神社(東大阪)
2025.02.20
-
 ON THE TRIP旅の体験をふくらませる音声ガイドアプリON THE TRIP とは、まるで美術館の音声ガイドのように、あらゆる旅先の神社や仏閣、絶景、あらゆる観光スポットで、その場で楽しめるオーディオガイドを提供。 アプリをダウンロードすれば、あなたのスマホが自分専用のトラベルガイドに!
ON THE TRIP旅の体験をふくらませる音声ガイドアプリON THE TRIP とは、まるで美術館の音声ガイドのように、あらゆる旅先の神社や仏閣、絶景、あらゆる観光スポットで、その場で楽しめるオーディオガイドを提供。 アプリをダウンロードすれば、あなたのスマホが自分専用のトラベルガイドに!
タイムトラベルは、ガイドを聴きながら大阪の旅を楽しんでいただける記事になります。本記事では音声ガイドの一部をお楽しみいただけます。オーディオ全編はON THE TRIPアプリで体験できます。
B-1|枚岡神社・拝殿(参道広場)
二ノ鳥居をくぐり、広い参道を進むと参道広場に出る。広場には「あげまき結び」という特殊な形のしめ縄が結ばれている。枚岡神社の主祭神は「アメノコヤネノミコト」と言い、神事を司る神様。しめ縄を用いた神話に深い関りを持つ神様でもある。
そんな神様にちなんで枚岡神社では、毎年 12月にしめ縄を新しく掛け替える「しめかけ神事」という祭りがある。別名を「お笑い神事」と言い、はじめに宮司が「アッハッハ」と大声で笑い、参拝者も続く。これを3回繰り返し、さらにその後、参拝者とともに思い思いに20分間笑い続けるのだ。1年の災難ごとを笑い飛ばし、福を招くために全国から多くの人が参加する。
これは岩戸の中に隠れてしまったアマテラスオオミカミが、アメノコヤネノミコトの神事と神々の笑いによって再び世に戻り、暗闇の世界に光が戻った喜びを再現した神事として太古から行われている。このことからアメノコヤネノミコトは日本で初めて神事を行った、神事を司る神となったのだ。

B-2|枚岡神社・御本殿
古代より豊かな水源に恵まれていたこの地は、大阪、河内(かわち)の国にとって特別な存在だった。生駒の山に雲がかかり雨が降り、その雨が土地を潤し、田畑が豊かに育つ。大和言葉で「ひ」は「神様のみたま」、「ら」は「たくさん」。神様の御霊(みたま)が満ちた場所という意味を持つ。農耕を行う民にとって、枚岡神社は「神のおわすところ」であった。
主祭神アメノコヤネノミコトは天の岩戸開きで活躍した後、アマテラスオオミカミから「てんそんほひつ」という使命を授けられる。これは「皇室の守護神」という意味で、その役割から平城京守護の春日大社創建時に分霊(ぶんれい)が祀られ、今では「元春日」とも呼ばれている。
境内からは、大阪平野が一望できる。実は枚岡神社から東の方角には奈良が、そしてそのずっと向こうには伊勢がある。境内からの美しい景色を眺めながら、神話の世界の繋がりを感じてみてほしい。

B-3|枚岡神社・出雲井(お釜殿)
拝殿から右に進むと、出雲井という井戸がある。この水を使い、室町時代から続く占い「かゆうら神事」が行われていた。かゆうら神事とは、毎年1月に行われる神事で、その年の天候と米や麦や大豆など53種類の作物の豊作凶作を占う。
大釜で小豆粥を煮て、かまどの火の中に12本の木を入れる。その焼け具合で各月の晴雨を占う。粥の中には53本の竹を束にして吊るし、炊きあがった際に竹筒に入った粥の量によって作物の豊凶を占う。では、なぜこの場所でこうした神事が行われていたのか。
それはここが、水源地であることが関係していたのかもしれない。こんな話がある。
大阪のある寺にずっと枯れていた井戸があった。しかし、急に水がわき、井戸から水があふれ出てきた。そしてその翌日、大きな震災が起こった。水の量が増える、水の色が変わる。水は天変地異の前触れを伝えてくれるセンサーとしての役割を持つ。
豊富な水を蓄える枚岡神社は、河内国にとって「神様のメッセージを受信する」適切な場所だったと言えるかもしれない。

※このガイドは、取材や資料に基づいて作っていますが、ぼくたち ON THE TRIP の解釈も含まれています。専門家により諸説が異なる場合がありますが、真実は自らの旅で発見してください。
※掲載情報は2025年2月時点のものです。掲載店舗・施設に関する最新の営業時間は各店舗・施設のHPなどでご確認ください。