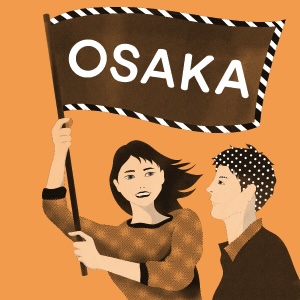うめきた公園に御堂筋のほこみち…変わりゆく大阪の公共空間の“たしなみかた”を都市再生のキーマンに聞いてみた
2025.03.31
大阪ではいま、街をうまく「使いこなす」都市開発が進行中。「好き」を突き詰めるマニアをゲストに大阪の魅力を深掘りする「OSAKAマニア探訪」、今回はランドスケープデザイナー・忽那裕樹さんが、大阪の公共空間の現在地をご紹介します。

2024年9月、先行まちびらきを迎えたグラングリーン大阪。大阪・梅田の一等地に誕生したこちらの複合商業施設は、4万5000平方メートルもの緑あふれる都市型公園・うめきた公園を中心に据え、都心における公共空間のこれまでにない活用法として全国から注目されています。
そのほかにも「水都」を象徴する中之島公園、ミナミの新しい顔ともいえるなんば広場など、大阪の街は公共の場が新しい「使いこなし」のできる場所になっています。自由に遊んだり、食事をしたりと、その価値は人が集い、思い思いに活かせる場であるという点に見出せます。そして、その魅力を支えるのはそれぞれの「公共」に寄り添うさまざまな知恵と工夫です。
今回のゲストはランドスケープデザイナーで、大阪・関西万博でもランドスケープデザインディレクターを務める忽那裕樹さん。大阪でいくつもの公共空間を生まれ変わらせてきたキーマンに、まるで生き物のように姿を変える大阪の風景を紹介してもらいました。
-
 忽那 裕樹(くつな ひろき)1966年、大阪府生まれ。ランドスケープデザイナー、株式会社E-DESIGN 代表取締役。公園、広場、道路、河川の景観・環境デザインと使いこなし、持続的なマネジメントシステムの構築を通して、新しい公共と魅力的なパブリックスペースの創出を目指す。主なプロジェクトに「水都大阪のまちづくり」(2016年 日本都市計画学会石川賞共同受賞)、「大東市公民連携北条まちづくりプロジェクト morineki」(2024年 日本建築学会賞共同受賞)、「シーパスパーク」(2024年 都市公園等コンクール 国土交通省都市局長賞/土地活用モデル大賞 国土交通大臣賞)など。
忽那 裕樹(くつな ひろき)1966年、大阪府生まれ。ランドスケープデザイナー、株式会社E-DESIGN 代表取締役。公園、広場、道路、河川の景観・環境デザインと使いこなし、持続的なマネジメントシステムの構築を通して、新しい公共と魅力的なパブリックスペースの創出を目指す。主なプロジェクトに「水都大阪のまちづくり」(2016年 日本都市計画学会石川賞共同受賞)、「大東市公民連携北条まちづくりプロジェクト morineki」(2024年 日本建築学会賞共同受賞)、「シーパスパーク」(2024年 都市公園等コンクール 国土交通省都市局長賞/土地活用モデル大賞 国土交通大臣賞)など。
01.中之島公園・中之島GATEサウスピア
生まれ変わった“遊べる”川辺で、いっそう深まる“水都”の魅力

水の都・大阪を代表する風景が広がる中之島公園。北を堂島川、南を土佐堀川に挟まれたエリアには、大阪市中央公会堂、中之島図書館といった近代建築や、東洋陶磁美術館、こども本の森 中之島、バラ園、カフェなどが揃います。活気ある大阪のイメージとはまた違う、ゆったりとした時間が流れる一帯が、最初に整備されたのは1891年。大阪市としては初の公園でした。

かつての水辺の交易拠点に生まれた公園の転換期は、21世紀を迎えた2001年。官民連携の都市再生プロジェクト「水都大阪のまちづくり」が始動し、古くから大阪の街の繁栄を支えてきた河川や水辺空間の再生が図られました。水都大阪の活性化にあたって主導的な役割を果たしたのが、忽那さんです。

忽那さんが中之島公園に関わるようになったのは2007年のこと。リニューアル前の中之島公園で実施されたプロジェクト「水都大阪2009」に準備段階から関わったのをはじめ、その後も中之島を舞台に、マルシェやイベントなどの社会実験的な試みを仕掛けたほか、カフェレストランの誘致を先導しました。




その後、2019年には中央公会堂から難波橋にかけての中之島通を歩行者空間化。シンボル的な建築の前にまるで「広場」のような歩道が出現し、空間の主役は人に変わりました。忽那さんの頭にあったのは、人が楽しめる場所づくりだったのです。中之島公園の芝生広場は出入り自由。当初は訪れる人に「芝生って立ち入ったらいけないんじゃ……」という先入観があったそうですが、徐々にそんな空気感もほぐれて、子どもや犬が戯れる場になっていきました。

一方で中之島の「西側」にも動きが。2025年4月には堂島川と土佐堀川が合流する安治川河畔に水辺のターミナル・中之島GATEサウスピアがオープンし、大阪・関西万博の会場である夢洲へ向かう船が運行されます。水都の持つ魅力を感じながら、世界的な祭典に参加できる体験はきっと特別なものになるでしょう。


02.御堂筋

関市長が築き上げたレガシーを“歩きたくなるセントラルパーク”に改革
大阪市内の中心を南北に貫く御堂筋。商都のメインストリートは、実は長らく横幅わずか6メートルの狭い筋でした。そこに開発の手を入れたのが、大正末期から昭和初期にかけて大阪市長を務めた関一(せき はじめ)。完成を見ぬまま在任中に死去しますが、1937年に御堂筋は幅44メートルという大通りに。のちに車社会の到来を受け、南側一方通行という大改造がなされています。
そんな御堂筋の一部で側道を閉鎖し、6車線の道路を4車線化する社会実験が始まったのは2013年。この一大プロジェクトにも忽那さんは関わっています。
計画が持ち上がる直前の御堂筋は、観光客の激増を受けて歩道がパンク状態に。反面、自動車の交通量は減少していました。それなら「歩行者の安全を確保しつつ、出店やパフォーマンスができるストリート、いわばセントラルパークをつくればいいのでは」との構想が提唱されたのです。


2020年には道路法が改正され、歩行者優先の道づくりを進める制度が創設。2025年3月時点で、なんば駅前から御堂筋と長堀通が交わる新橋交差点にかけての側道を歩道化し、さまざまな使い方ができる「ほこみち」と呼ばれる道にしていく計画が進行中です。結果として、かつて道路としての機能しかなかった場所で、キッチンカーイベントやストリートパフォーマンスが行われるようになりました。

歩道の道幅が広がったことで道に公園としての機能が加わり、楽しみ方の幅が広がったともいえるでしょう。沿道の街づくり団体はエリアごとに別々の動きをしていましたが、忽那さんの働きかけで話し合いが持たれ、「車の道から人の道へ」「いろいろな使いこなしのできる道へ」という思いが共有されたことも、一体感ある再開発を可能にしました。
時代に合わせて、歩いたり、たたずんだりする楽しみが格段に増しつつある新しい御堂筋。完成から100周年を迎える2037年には、キタエリアを含む通り全体の完全歩道化が構想されています。


03.なんば広場
大阪の玄関口だからこそ現実になった、誰もが演者になれる新しい“舞台”

なんば駅前のタクシープールや車道を再編することで、2023年に人のための広場として誕生したのが、その名もなんば広場。使う人が自由に移動させていいテーブルやベンチ、段差や角度を利用して思い思いの座り方ができるテラスベンチ、植栽帯が設けられ、待ち合わせや休憩にぴったりな都市景観が広がっています。


この再開発は周辺の商店街や組合の事業者が発案し、鉄道会社とも協働、警察との間で何度も話し合いが重ねられた末に完成しました。



階段状の巨大なテラスベンチは、忽那さんにいわせれば「舞台」とのこと。偶然その場をともにする人々が好きなように腰掛け、仕事をしたり、食事をしたりと、さまざまな「シーン」が繰り広げられます。構想15年、何度も何度も図面を書き換えたという綿密な設計思想と仕掛けが、なんば駅前に新たな舞台を生んだのです。



なんば広場のコンセプトは「憩い・出会い・生み出す 大阪発のリアルメディア」。遊びに仕事に、誰もが演者になれるこれまでにない「メディア」は、そこを通る日常から多種多様なイベントという非日常までを彩る、大切な役割を果たしていくことでしょう。
04.SHEEPATH PARK
市民との共創と実験という営みで形づくる“やれないことのない公園”

最後に紹介するのは、大阪市の中心部から電車で30分ほどの泉大津市に2023年に開園したSHEEPATH PARK(シーパスパーク)。かつての市民会館跡地を活用してできた3.5ヘクタールもの憩いの場は、行政と街の人が一緒に運営しているのが特徴です。忽那さん率いるE-DESIGNが公園のデザインおよび指定管理者として公園運営も担っています。広場には、感度の高いショップやレストランが。都市公園法の改正が後押しになり、地域住民が公園づくりの主人公になったのです。



その言葉の通り、園内には高低差のある芝生広場、泥遊びのできる「どろんこリング」、水と戯れる「じゃぶじゃぶリング」といったエリアが盛りだくさん。「シーパス山」は芝滑りにもパークを一望するのにも使え、使い方に正解はありません。また、あえて目立った遊具は置かず、そり、ゴムボールなどの外遊びグッズの貸し出しを行っていること、シャワールームや更衣室があるのも特徴的です。そして、多くの公園で見られがちな禁止事項が少なく、訪ねる人が自由に過ごし方をつくり出せることもSHEEPATH PARKならではです。

忽那さんの言葉を借りれば、SHEEPATH PARKは「実験ばかりする公園」。その積み重ねが、まだできて間もない公園の自由な未来を描き出すはずです。

“新しい公共空間”を使いこなそう

忽那さんが「これからの都市開発は緑抜きには語れない」と話すように、うめきた公園というシンボリックな「緑の器」が出現したことにより、改めてスポットライトが当たる大阪の公共空間。3月21日に「グラングリーン大阪 南館」と「うめきたグリーンプレイス」が開業し、中核機能施設「JAM BASE」の一部である都市型MICE施設もオープンしました。

そうした場の「かたち」と「しくみ」が入念にデザインされ、そこで遊んだり、楽しんだりと訪れる人がそれぞれの「うごき」を加えれば、空間の持つ自由度は大きく膨らむことでしょう。

今回取り上げたスポットは、いずれもそこに集う人たちが主人公。より自由度が高まりゆく公共空間を、自分らしく使いこなしてみてはいかがでしょうか。
- Text
- 関根デッカオ(Deccao Sekine)
- Photo
- 平野明(Mei Hirano)
- Edit
- 島田彩(Aya Shimada)
- Direction
- 人間編集部